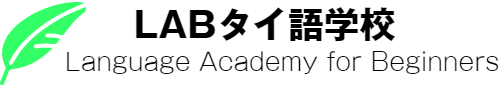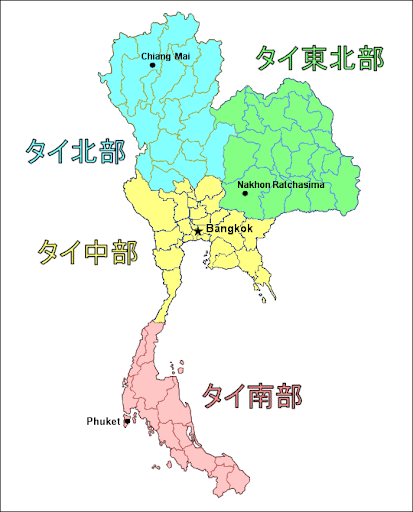「タイの朝食屋台」完全ガイド|地元で人気の定番メニュー&歴史も解説!
サワディーカー!LABタイ語学校です。
本日は、タイでよく見かける屋台のなかでもサクッと食べれる「朝食」に最適な料理を、いくつか紹介します。
【屋台で使えるタイ語フレーズ①】
เอาอันนี้ค่ะ/ครับ
アオ・アン・ニー・カ/クラップ
(意味)これをください
เอากลับบ้านค่ะ/ครับ
アオ・グラップ・バーン・カ/クラップ
(意味)持ち帰りでお願いします
🍳 タイの朝食屋台は「軽め×手早い」が基本!
タイでは、朝の屋台文化がとても根付いており、特に6:00〜10:00頃が一番賑わう時間帯といわれています。会社員や学生など、通勤・通学前に立ち寄る人でいっぱいです。
屋台の多くは午前10時を過ぎると閉店してしまうため、朝の時間帯だけの“限定風景”ともいえます。
タイの朝食屋台の魅力は、なんといっても「軽めで手早い」ことです。
多くの人が「出勤・登校前にサッと買って食べる」スタイルなので、持ち帰りしやすい料理や、すぐに食べられる一皿メニューが中心です。例えば、スプーン一つで食べられる「ジョーク(おかゆ)」や、袋入りで渡される「カオニャオ・ムーピン(豚串ともち米)」などは定番の人気メニューです。
屋台によってはコーヒーや豆乳などのドリンクも販売しています。
タイの朝食屋台は「時間がない朝でもしっかり食べたい人たち」の強い味方なのです。
屋台でよく売られている朝食メニュー
カイガタ(ไข่กะทะ)
「カイガタ」は、元々ベトナムに起源があると言われている鉄板目玉焼きセットで、ベトナムからラオスへと伝わったのち、タイ東北部のイサーン地方に伝わり、今では全国で親しまれています。
(カイガタ)
小さなアルミパンの上で焼かれる半熟の卵に、ウインナー・ひき肉・チャーシュー・ねぎなどがトッピングされています。
食べ方はスプーンでそのまま食べるか、パン(ขนมปัง/カノムパン)が添えられている場合はディップして食べるのもおいしいです。
最近では、カフェ風におしゃれにアレンジして提供するお店も増え、写真映えする朝食としても人気です。
イサーン料理文化が残る屋台(エカマイ・アーリー・チャトチャック周辺にもあり)で多く見かけることができます。
カオトム(ข้าวต้ม)
=米入りスープ(「汁多めのおかゆ」)のことを指します。
(カオトム)
ジョーク(とろとろ粥)よりも米粒がしっかりしていて、やさしいスープの味が朝の胃にしみわたります。
具材は豚、魚、イカ、エビなどが定番で、仕上げでショウガ・パクチー・揚げにんにくなどがトッピングされます。
あっさりした中に旨味が凝縮されていて、朝から心も体も温まりますね。
パートンコー(ปาท่องโก๋)
=タイ風揚げパンを指します。
(パートンコー)
“タイの朝の定番コンビ”と言われているのが、パートンコー+豆乳のコンビです。
タイの朝食の定番スナックといえば、やはり「パートンコー」です。
小さなツイン型の揚げパンで、外はカリッ、中はふんわりな食感がたまりません。パートンコーは、甘い練乳をつけたり、豆乳(นมถั่วเหลือง/ノムトゥアリアン)やタイミルクティー(ชาเย็น/チャーイェン)などと一緒に食べるのがタイの朝食の定番スタイルです。
特に朝のコーヒー屋台や豆乳屋台では「パートンコー+ドリンク」が黄金の組み合わせ。
軽いけれど満足感たっぷりの朝の一品です。
またパートンコーは、屋台だけでなくマクドナルドでも食べることができます。マクドナルドの朝マックメニューでも根強い人気を誇っています。
カイヤータオ(ไข่ดาว)・カオムーデーン(ข้าวหมูแดง)
=ご飯もの朝食を指します。
ご飯派の人に人気なのが、目玉焼き+ご飯ものの組み合わせ。
カイヤータオ(=目玉焼き)、カオムーデーン(=赤豚丼)やカオカイチアオ(=卵焼きご飯)の上にのせると、より満足感のある朝食になります。
(カイヤータオ)
(カオムーデーン)
(カオカイチアオ)
赤い甘辛タレがかかったチャーシューご飯(カオムーデーン)や、カリカリ豚のせご飯(カオムークロップ)も屋台の定番となっています。
ノムトゥアリアン(นมถั่วเหลือง)
=豆乳ドリンクを指します。

タイの屋台ではおなじみの豆乳ドリンク。
温かい豆乳に黒糖シロップを加えたやさしい味わいで、甘さ控えめに調整してもらうことも可能です。
お好みで白きくらげ、タロイモ、タピオカなどをトッピングする人も多く、軽い朝食としても人気です。
「飲む朝ごはん」として、忙しいタイ人の朝を支えています。
🇹🇭 タイの朝ごはん屋台の歴史
① 屋台文化のはじまり
今でこそ「ストリートフードの王国」と呼ばれるタイですが、その原点は19世紀後半〜20世紀初頭(ラーマ5世時代)にさかのぼります。
当時のバンコクは、まだ水上交通が中心の「運河の街」でした。船で行き来する人々に向けて、水上マーケットで食事を売る商人たちが現れました。この“水上屋台”こそが、のちのストリートフード文化の原型です。
やがて時代が進み、陸上交通が発達すると、中国系移民(とくに潮州系)たちがバンコクに多く移り住み、陸に屋台を出して麺料理や粥(ジョーク)、肉まんなどを販売するようになります。
こうして、タイの街角には次第に鉄鍋や香草の香りが漂い始め、人々は屋台で朝食をとる習慣を自然に身につけていきます。
のちにタイ人の商人や家庭料理人もこの文化に参入し、地域ごとの朝ごはんスタイルが形成されました。バンコクではおかゆ、イサーン地方では鉄板焼き卵「カイガタ」、北部ではカレーラーメン「カオソーイ」など、土地ごとの個性が生まれたのです。
つまり、「朝食屋台=中華系移民の知恵が根づいた生活文化」と言えます。
②朝ごはん屋台が発展した理由
タイでは昔から、朝の食事をとても大切にする文化があります。「朝ごはんを抜くと元気が出ない」という考えが一般的で、どんなに忙しくても、コーヒーと揚げパン、あるいはおかゆだけでも口にします。
しかし、都市化が進むにつれ、家で朝食を用意する時間がなくなり、屋台で買って食べるスタイルが日常に定着しました。
特に、バンコクのような大都市では共働き家庭が多く、通勤ラッシュも激しいため、「通勤途中でサッと買える」「職場や学校で食べられる」屋台の存在が欠かせません。
朝の時間帯(🕕5時〜9時頃)になると、通りの角や学校の前、BTS駅の近くなどにはずらりと屋台が並び、白い湯気と香ばしい匂いが立ちこめます。
人々はバイクで横づけして持ち帰ったり、プラスチック袋に入ったスープやおかゆを片手に歩いたり。この風景こそ、タイの朝の象徴的な光景です。
また、タイ人は温かく・軽い食事を好む傾向があり、消化の良いおかゆやスープ、蒸し料理などが朝の定番です。「朝に辛いものは避ける」という人も多く、屋台のメニューも自然とマイルドな味付けが多くなっています。
③地域によって違う朝ごはん文化
-
北部(チェンマイなど):カオソーイ(カレーラーメン風)、カオトム(ライススープ)など
-
東北部(イサーン):カイガタ、もち米+ソーセージ(サイクロークイサーン)
-
南部(ハジャイなど):肉まん、点心、ホットティー文化が強いです。
🧭 旅行中、地方によって「朝ごはん屋台」がガラッと変わるのも魅力ですね✨
最後に
今回は、タイの「朝食屋台」について詳しく紹介しました。
朝食メニューがとても豊富でさまざまな楽しみ方があり、かつ時短でサクッと楽しめるのはタイの朝食屋台の大きな魅力です。
タイへ旅行に訪れた際は、少し早く起きて近くの屋台で朝食を楽しんでみるのも面白いかもしれませんね!✨
【屋台で使えるフレーズ②】
เท่าไหร่คะ/ครับ
タオ・ライ・カ/クラップ
(意味)いくらですか?
ลดหน่อยได้ไหมคะ/ครับ
ロット・ノーイ・ダイ・マイ・カ/クラップ
(意味)少し安くしてもらえますか?