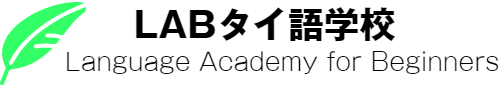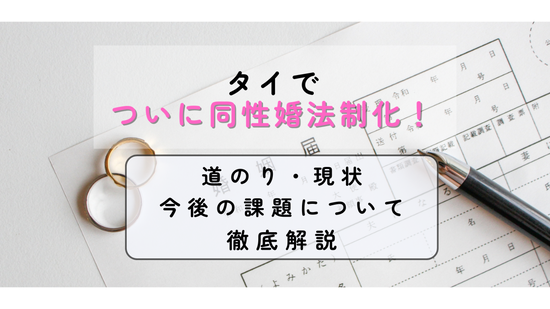【2025年最新】タイ同性婚法制化!道のり・現状・今後の課題について解説
サワディーカー!LABタイ語学校です。
ついに2025年1月23日に東南アジアで初の同性婚法制化がタイで行われました。法制化されるまでのタイでの動きや何が変わったのか、今後の課題について詳しく解説していきます。
それでは解説していきましょう。
ยินดีด้วยกับการแต่งงาน
インディー ドゥアイ ガップ ガーン テンガーン
結婚おめでとう
คุณมีคู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยม
クン ミー クー チーウィット ティー ヨーット イーム
素敵なパートナーですね
結婚に関する表現のタイ語音声と動画はコチラ
同性婚が法律になるまでの道のり
タイはLGBTQ+に寛容な社会として世界に知られています。しかし今まで伝統的な家族観や宗教などの影響から、同性婚法制化の活動に積極的ではない人たちも多くいました。では同性婚が法制化するまでどのような活動が行われていたのでしょうか。
LGBTQ+とは、セクシュアルマイノリティ(性的少数者・性的マイノリティ)を表す総称のひとつで、以下の頭文字をとった言葉です。
Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)
Gay(ゲイ、男性同性愛者)
Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)
Transgender(トランスジェンダー、出生時の性別や、その性別に期待されるあり方とは異なる性別で生きている・生きたい人)
Queer(クィア、規範的な性のあり方以外のセクシュアリティ)
Questioning(クエスチョニング、自らの性のあり方について特定の枠に属さない人、わからない人、決めたくない人)
+(「L・G・B・T・Q」に当てはまらない多様な性)
初めての同性婚法案提出
2012年にタイで初めて同性婚法案の提出がされました。当時タイはLGBTQ+に比較的寛容な社会になってきていました。
また2010年にアイスランド、2012年にはデンマークが同性婚を合法化するなど、欧米諸国で同性婚が認められるようになってきていました。こうした国内外の動きを受け、2012年にタイ議会で同性婚を合法化するための法案が初めて提出されました。
結果的に優先順位の低さや世論などの影響で成立にはいたりませんでしたが、以降同性婚についての議論が活発になり同性婚法制化への一歩であったと言えます。
シビルパートナーシップ法
タイでは過去に2度シビルパートナーシップ法について国会で審議を行っていました。
シビルパートナーシップとは、一部の法的権利を同性カップルに与える制度のことです。同性婚は「同性愛者にも異性愛者の結婚と同等の権利を認めるもの」なので、シビルパートナーシップではすべての権利が与えられるわけではありません。
2018年から法案についての議論が始まり、2020年に一度法案が国会で審議されましたが、最終的には成立しませんでした。2022年に再び法案が国会で審議されましたが、政局の影響などもあり、完全に成立するには至りませんでした。
シビルパートナーシップ法が議論され始めた当初は、タイ政府は「シビルパートナーシップの方が社会に受け入れられやすい」というふうに考えていました。しかし、多くの当事者やLGBTQ+団体などが「異性愛者と同じ権利を持つべきだ」「中途半端な妥協案ではなく、完全な婚姻の権利を認めるべきだ」と主張し、シビルパートナーシップではなく完全な同性婚の合法化を求める声が強まりました。
その結果シビルパートナーシップ法を導入するよりも、2025年に東南アジアで初めて同性婚が合法化されました。
2020年~ 同性婚法制化への活動が活発に
アジアでは2019年に初めて台湾が同性婚を合法化し、タイ国内でも大きな影響を与えました。この頃からタイでは若者を中心にLGBTQ+への理解が深まり、同性婚法制化を求める声が強くなっていきました。特に、民主化を求める学生運動と連動する形で、LGBTQ+の権利を求めるデモが頻繁に行われるようになりました。
この動きにより、タイ政府も同性婚に関する議論を無視できなくなっていきました。
2022年:同性婚法案が初めて議会を通過
2022年には初めて同性婚法案が議会を通過しました。議会に提出された法案は「シビルパートナーシップ法案」とは異なり、同性カップルを異性愛カップルと同等に完全な結婚の権利を認めるという内容でした。
法案は国会で審議され、初めて下院を通過しました。しかし、2023年に行われる総選挙などの影響で与党が慎重になり、上院での審議が進まず最終的に法案は成立しませんでした。
ですが、このことがきかっけとなり2023年の総選挙では同性婚の合法化を公約に掲げる政党が増え、同性婚合法化に向けた大きな前進となりました。
2023年:総選挙
2020~のデモや同性婚法案が通過したことなどの影響から、2023年の総選挙では同性婚の合法化を公約にする政党も出てきました。同性婚の法制化を支持する議員が増えたことで、法案が通りやすくなりました。
同性婚が認められて何が変わったのか
これまでタイでは同性カップルは法的に結婚できず、長年生活を共にしていても法律上は「他人」という扱いを受けていました。しかし2025年1月23日に「結婚平等法」が施行され同性婚が認められたことで、法律上で正式に夫婦として登録できるようになりました。これにより、戸籍上でも家族として認められるということになります。
では同性婚が法制化したことにより、何ができるようになったのか、どのようなことが変わったのでしょうか。
「夫・妻」の表記が「配偶者」へ
結婚平等法の条文では「男性」や「女性」を「個人」と表現されており、婚姻届や戸籍謄本などの書類に関しては「夫」「妻」という欄を性別に依存しない「配偶者」という表記に変更されることとなりました。これによって同性カップルも異性カップルと同等の権利を得ることが出来ました。
姓の変更
今まではあくまで他人となっていましたが結婚することができるようになり、配偶者の姓へ変更することが認められるようになりました。
結婚証明書の発行
同性カップルも婚姻登録ができるようになり、結婚証明書を発行することが出来るようになりました。
相続権
同性婚が法制化する前は同性カップルの一方が亡くなった場合、残された方には法的な相続権がありませんでした。そのため、遺言書を作成していない限り、亡くなったパートナーの財産は家族や親族に渡ってしまい残されたパートナーは何も相続されないという場合が多くありました。
しかし、法制化したことにより異性カップルと同じように配偶者としての相続権が法的に認められるようになりました。これによって残されたパートナーの経済的な不安が減少することになります。
医療や保険の権利
法制化する前はパートナーが病気や事故に遭い手術を受けることになった場合、家族しか意思決定をする権利はなく、パートナーには医療判断を下す権利がありませんでした。実際にパートナーが事故に遭い病院に行った際、病院から手術の同意書に署名できるのは家族のみと言われ家族を待つことしかできなかった、というケースもありました。
ですが、法制化し配偶者と認められるようになったことで以下のことが出来るようになりました。
・医療判断の権利:配偶者としてパートナーの医療判断、手術の同意をすることが出来る。
・病院での面会権:家族と同じように、パートナーの面会を配偶者としてすることが出来る。
・健康保険の適用:健康保険や企業の福利厚生などに関して、配偶者として保険が適用される。
養子縁組の権利
同性カップルが法的に結婚が認められるようになったことで、異性カップルと同じように養子縁組をする権利が認められるようになりました。
これにより、さらに多様な家族の形が認められるようになったということになります。
この他にも配偶者は税控除など政府が提供する社会保障の権利、年金などの手当てを受ける権利など異性カップルと同等の権利が認められるようになりました。
今後の課題
トランスジェンダーの性別変更
タイでは同性婚は認められたものの、まだ性別の変更は法的に認められていません。戸籍や身分証明書には出生時の性別が記載されているため、空港などでトラブルになる場合もあります。
またタイには徴兵制度が存在しています。徴兵制度は21歳の男性から選ばれ、希望者と徴兵検査で身体検査に合格をして「くじ引き」の結果で兵役に就くことが決まります。身体検査の上で性転換手術済みのトランスジェンダーであることが認められると兵役が免除されます。
しかし、性別の変更が出来ず公的な書類には男性と記載されるため、診断書を提出するために徴兵検査の会場へ行かなくてはならないことに不満を感じている人も少なくありません。またトランスジェンダーで性転換手術が終わっておらず抽選で当たってしまった場合は徴兵へ行かなくてはなりません。
企業の対応
タイでは、2015年に「ジェンダー平等法」が施行され、職場や学校でのLGBTQ+に対する差別を禁止する法律が制定されました。しかし現在でも完全に差別がなくなったということはできません。いまだに企業がトランスジェンダーという理由で採用をしなかったりする場合もあります。
また今年1月に同性婚が法制化したため、企業側がまだ対応に追いついておらず同性婚をしたカップルが福利厚生を受けられないという企業もあります。同性カップルに対しても福利厚生を受けることが出来るように、福利厚生制度の見直しをする必要があります。
最後に
いかがでしたか?
今回は2025年1月23日にタイで法律になった同性婚について解説しました。
タイの同性婚については日本でもニュースで取り上げられていました。
多様性を尊重するタイの動きが、今後アジアにどのような影響を与えるのか注目です。